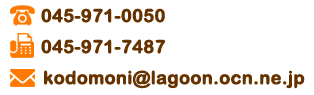私たちの身の回りには豊かな自然、素晴らしい芸術や文化が溢れています。それらをできるだけ多くの子どもたちに伝え遺すことは、私たち大人の大切な使命だと考えています。
しかし、現在子どもたちが置かれている教育環境を見ると、暗然たる気持ちになります。テストの点数至上主義の傾向は一向に改まらず、子どもたちの人間性や個性、更には人間として最も大切な心といった部分が置き去りにされてしまっているように思えてなりません。
点数を取ることよりも、心を豊かに、人間が人間である証の感性を豊かに培っていくことが大切ではないのでしょうか。それには小さい頃から芸術や自然に親しみ、身をもってそれらの素晴らしさを受け取る機会をより多く持つことが大切と考えます。


長年クラシック音楽に関わってきた発起人(現理事長)は、自分に何か出来ることはないだろうか、と思いを巡らしその結果、子どもたちにクラシック音楽を聴いてもらう、それも一流の演奏家による生の演奏で、という考えに至りこの「NPO法人子どもに音楽を」を立ち上げました。こうした私たちの考えに、世界の第一線で活躍する多くの演奏家やNHK交響楽団のメンバーなどからご賛同いただいています。積極的に、子どもたちと演奏家を「繋ぐ」場を提供していきたいと思います。
会場は大きなホールなどでなく学校の音楽室や体育館です。子どもたちには楽器が持つ魅力ある音と響き、さらに演奏家の息遣いまでも出来るだけ身近に直接全身で感じて欲しいのです。子どもたちにとって人間の心と身体から紡ぎだされる音楽はより強く印象づけられ、心に深く残るに違いないと思います。1回限りの大規模なコンサートを開くことより、むしろこうした小規模なものを多く開き、それも10年、20年と息長く続けることで、花開き実を結ぶような活動にしたいと考えます。

加えて今のクラシック音楽界は、優秀な若い演奏家がたくさん生まれてきているにもかかわらず、彼らは演奏する機会に必ずしも十分恵まれているとは言えない残念な状況にもあります。 彼らの為に演奏の機会を1回でも多く作っていくことも今後の活動の目的に加えたいと思います。
私たちの活動によって子どもたちの心の中に優しく豊かな感性が芽生え、育まれていくことを願っています。皆さま方のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
2006年7月5日
NPO法人「子どもに音楽を」理事長 徳永扶美子